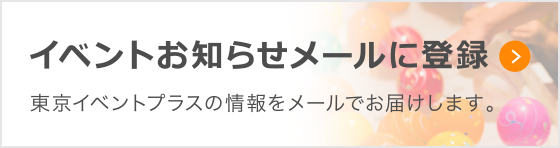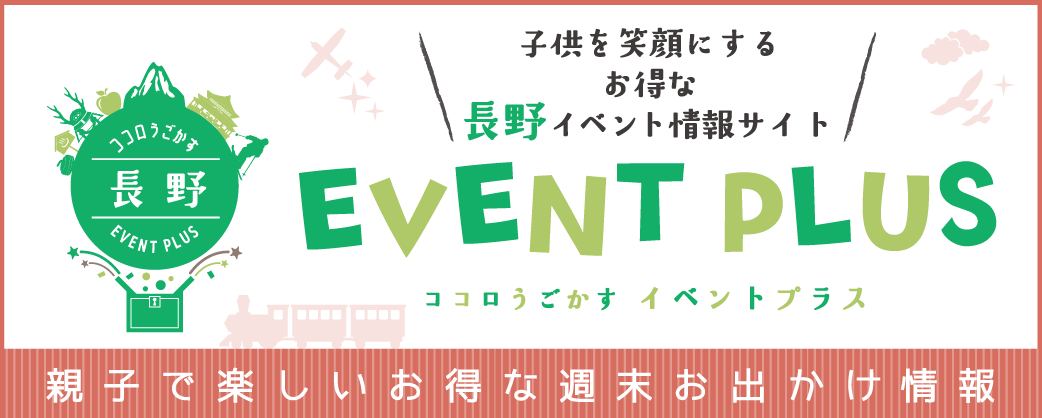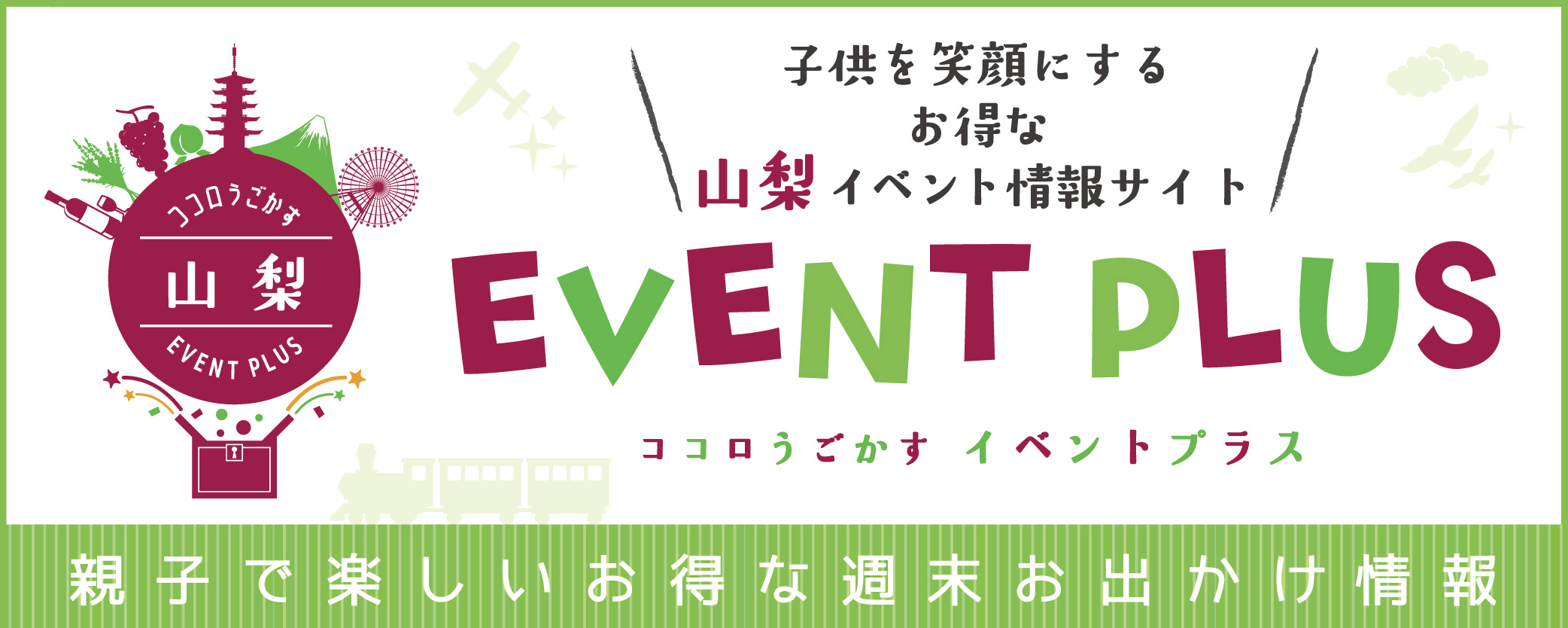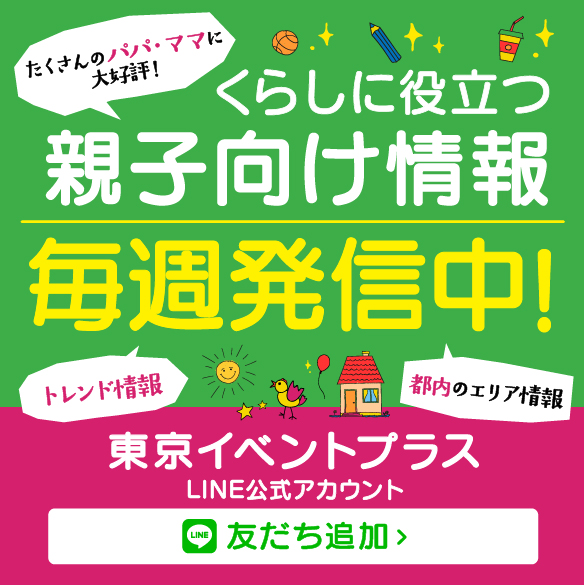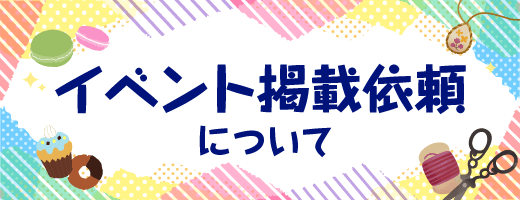カブトムシの幼虫を育ててみたいけれど、「何を準備すればいいの?」「どんな環境が必要?」と不安に思っていませんか?本記事では、カブトムシの幼虫の育て方を初心者にもわかりやすく解説します!
カブトムシの幼虫は、成虫と比べると見た目にインパクトがありますが、その成長過程を自由研究などにして観察するのも楽しいですよ♪
育成にはいくつかのポイントがありますが、コツを掴めば初心者でも簡単に飼育できます。
本記事では、必要な道具の準備から、成虫になるまでの成長過程、日々の飼育ポイントまで徹底解説!さらに、幼虫の健康管理や、オスとメスの見分け方、飼育の際の注意点なども詳しく紹介します。
カブトムシの飼育を成功させ、大きく元気なカブトムシを育てましょう!
※ここからはカブトムシの幼虫の写真が出てくる場面もありますので、苦手な方はご注意ください。
目次
カブトムシの一生
9月 1令幼虫(初令幼虫)
カブトムシの産卵後、2週間ほどで卵が割れて幼虫が出てきます。
これを1令幼虫と呼び、体長は約8~10mm程です。

9月~10月 2令幼虫
1令幼虫は、1週間程で脱皮を行います。脱皮後の幼虫を2令幼虫と呼びます。
体には、たくさんの細かい毛があり、周囲の状況を感じることができるようになります。

10月~5月 3令幼虫
2令幼虫は3週間ほどで2度目の脱皮を行います。この脱皮後の幼虫を3令幼虫と呼び、最初の体長は約40mm程です。
3令幼虫は自身の大きなあごを使いながら腐葉土などをたくさん食べて、体長は8~12cmにまで成長します。
カブトムシの成虫は幼虫期にどれだけ大きくなるのかが重要で、幼虫が大きく成長すればその分、カブトムシが成虫になった時に大きく立派なカブトムシになると言われています。
そのため、この時期に餌である腐葉土や幼虫マットをきらさないようにしましょう。
3月~4月の温かい春頃になると、幼虫の白い体が少し黄色になってきますが、これはちゃんとサナギに成長しているサインです。

5月~6月 サナギ
蛹室を作ってサナギになっていくので、幼虫たちを刺激しないようにマット交換はストップしましょう!
サナギはとてもデリケートなので触ったり、振ったりしないよう動かさず観察しましょう。

6月上旬~ 羽化
サナギから成虫なるまでは大体2週間~1か月程かかります。羽化したばかりの成虫はしばらくはじっとしており、まだ体が柔らかいのでこの時期もなるべく触らないようにしましょう。
体が硬くなり、動くようになってきたら成虫用の飼育セットに移動させましょう。

準備するもの
・飼育ケース または 2Lペットボトル
・幼虫マット または 腐葉土
・霧吹き
※これらはペットショップやホームセンター、ネットショップなどで購入できます。
カブトムシの幼虫の育て方
【飼育ケースづくり】
①飼育ケースに10~15センチほど幼虫マットか腐葉土を入れる。
②霧吹きなどで水分量を整えます。手で握った時にそのまま形が崩れないぐらいが適量です。
③カブトムシの幼虫をマットの上に優しく置いてあげます。
徐々に自分でマットの中に入っていくのでそのままで大丈夫です。
④カブトムシの幼虫がマットに潜ったら蓋をします。
この時に蓋とケースの間に新聞紙やキッチンペーパーをはさむとコバエの侵入防止などに効果があります。
※土の表面が乾燥してきたら霧吹きで水をかけて幼虫の暮らしやすい環境づくりを目指しましょう!
幼虫は1つのケースに何匹も入れてしまうとストレスにつながって育ちにくくなる可能性もあります。そのため、できれば一匹ずつの飼育をおすすめしますが、1ケースに小さめの幼虫4匹程度なら同時に飼育も可能です。
【ペットボトルでの育て方】
※ペットボトルでの飼育をされる方は、2ℓのペットボトルの上部を切って、飼育ケースと同じ要領で準備をします。ペットボトルでの飼育は単体での飼育をおすすめします。
【幼虫の飼育ポイント】
①腐葉土の水分量は一定に!手で握っても形が崩れず、しっとりとした状態を維持しましょう。
②急激な温度変化を避けるため、直射日光の当たらない室内での飼育がおすすめ!
③腐葉土の状態はカブトムシの幼虫にも影響するので、腐葉土が乾いてきたら霧吹きをする、腐葉土に糞がたまってきたら腐葉土を交換することを心がけましょう。
【どこで育てるのがベスト?】
屋外だと気温の変化が激しかったり、雨で水没してしまうリスクがあるので屋外はなるべく避けた方がいいです。
室内の温度変化が少なく直射日光が当たらない場所で飼育しましょう!
【昆虫マットの交換の頻度は?】
飼育ケースにカブトムシの幼虫の糞が目立ってきたら、新しい幼虫マットか腐葉土に変えてあげましょう。カブトムシの幼虫の糞は楕円形の粒状になっています。
【カブトムシの幼虫のオスとメスの見分け方】
カブトムシの幼虫は、外見上の違いはほとんどないので見分けることが難しいです。
オスの幼虫の場合、お尻から少し上の2番目と3番目の線の間にVの印があることが特徴です。
メスの幼虫はオスのように印がないのがほとんどですが、おしりに白い点が浮き出ているメスの幼虫もいます。
【成虫になったら】
成虫になったら、エサ(ゼリーなど)を用意し、新たな飼育環境を整えます。元気に飛び回るカブトムシの姿を観察しましょう!
【土の中から出てくるあの現象は!?】
カブトムシの幼虫を飼っていると、たまに幼虫マットからカブトムシの幼虫が出てくることがあります。
マット交換を忘れていて、マット内の環境が悪くなってしまっている場合や単に新鮮な空気を求めて地上に出てくる場合もあるので、その場合は容器の蓋に穴をあけて通気性をよくするなど改善してあげましょう。
まとめ
カブトムシの幼虫の育成は、手間がかかるように見えますが、ポイントを押さえれば初心者でも簡単に育てられます。初めての飼育で心配な方は1匹ずつ育てる方がいいかもしれません。
しっかり環境を整え、大きく元気なカブトムシを一緒に育ててみましょう!
カブトムシ・クワガタグッズの買い方がわからない人はこちらをクリック⤵
初めてさんでも大丈夫!カブトムシ・クワガタの正しい飼育法・注意点
2025年3月カブトムシの幼虫がもらえちゃうイベントはこちらから!
・2025年3月1日(土)~3月2日(日)|環八蒲田住宅公園
・2025年3月1日(土)~3月2日(日)|ハウジングプラザ瀬田
・2025年3月16日(日)・3月20日(木祝)|オークラランド住宅公園